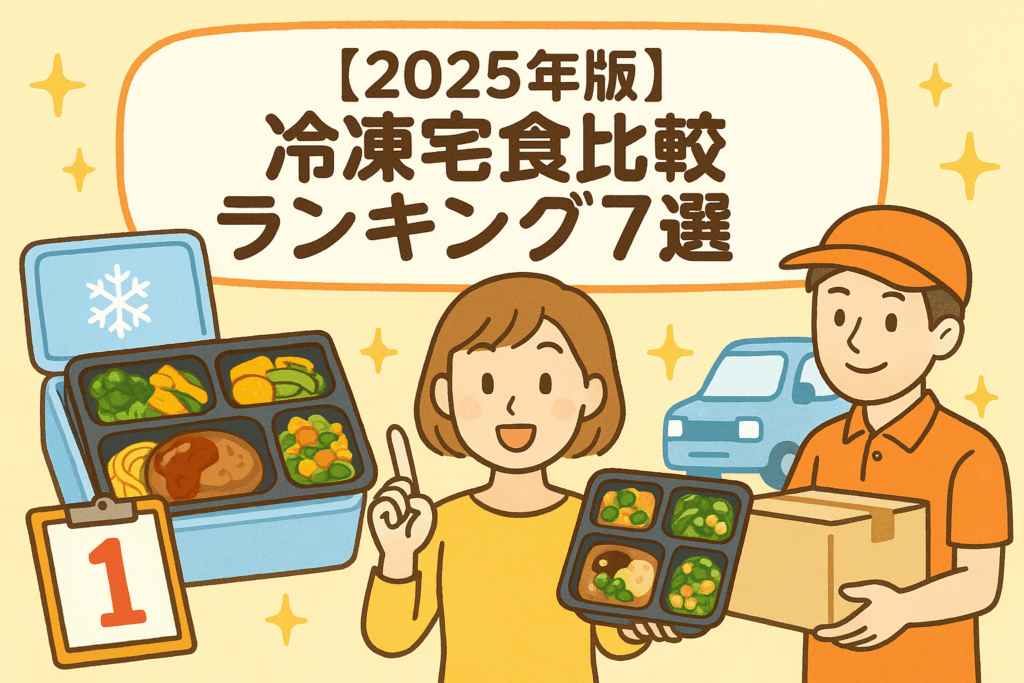
※このページはプロモーションを含みます。
まずは各社の特徴を把握し、「自分の生活リズム(平日の昼・夜、週末のみ等)」「好みの味付け・主菜の傾向」「送料込みの1食あたり目安」を照らし合わせて選ぶのがおすすめです。冷凍庫の空き容量に合わせたセット数や、定期便のスキップ機能の有無にも注目すると失敗しにくくなります。
選定基準(冷凍宅食サービスであること・配送対象範囲・評価軸)
価格面では、セット価格と送料の合計から「1食あたり目安」を算出して検討し、定期便値引きやクーポン施策の有無もチェック。メニュー面では、主菜の傾向(魚/肉/和洋中)や副菜の種類、季節メニューの入れ替え頻度など、飽きにくさも指標にしました。調理面は、レンジ出力(W)と加熱分数の明記、袋の切り口やトレーの扱いやすさ、やけどしにくい構造など、日常使いでストレスが少ないかを確認。以上を総合して順位付けしています。
各サービスの特徴比較(価格・メニュー・配送条件 等)
配送条件は、お届けの曜日指定・時間帯指定の可否、クール便区分、再配達の扱いなどをチェック。トレー寸法やパッケージ厚みは冷凍庫事情に直結するため、まとめ買いの場合は庫内レイアウトを事前に想定しておくと安心です。なお、1食ずつ個包装か、複数食まとめて箱入りかでも取り回しが変わります。
こうした比較観点を踏まえ、1位の「ワタミの宅食ダイレクト」は、管理栄養士が献立設計している点、全国(※一部地域除く)へ宅配便で届く点、お休み・変更OK/手数料・解約金0円(案内に基づく)といった続けやすい仕組みが魅力。“冷凍庫にあると安心”という日常ニーズに応える総合力で、ランキングの基準に合致しています。
利用の注意点(送料、配送エリア、解凍・調理方法 等)
受け取りは、日時指定や置き配の可否を確認し、再配達の手間を抑える工夫を。留守が多い家庭は、「週末受け取り→一週間分をストック」の運用が便利です。トレーをお皿に移し替えると見た目が整い、食卓の満足度も高まります。
利用想定ユーザー(独身・共働き・高齢者など)
冷凍保存と解凍のポイント
食べきれなかった分の再冷凍は基本NG。品質保持のため、必要な分のみ解凍する運用が理想です。賞味期限は製品ごとに異なるため、箱やトレーの表示を参照し、先入れ先出しでロスなく使い切りましょう。
1位 ワタミの宅食ダイレクト(ワタミ株式会社)

出典:ワタミ株式会社
価格・送料(1食あたり目安・送料・割引制度 など)
まず押さえたいのは「続けやすさ」。ワタミの宅食ダイレクトは、冷凍の惣菜セットを中心にラインナップされ、宅配便で全国(一部地域を除く)にお届けします。セット価格に送料が加わる仕組みのため、利用地域や箱数・温度帯によって実際のお支払いは変動しますが、“まとめて受け取って冷凍庫にストック”できるのが大きな魅力。
定期利用では、お届け頻度が選べるうえ、お休み・変更OK、さらに解約に手数料がかからないのがうれしいポイントです。まずは生活リズムに合わせて「月1回」「2週間に1回」などマイペースに設定し、冷凍庫の容量に合わせてセット数を調整するのがおすすめ。
1食あたりの体感コストを考えるときは、セット価格+送料を合算し、冷凍庫に入るトレー枚数と消費ペースで割るのがコツ。お得なキャンペーンや定期割引が実施されるタイミングもあるため、まずは公式ページで現在の施策を確認しながら、ご自身の頻度・数量に最適化するとムダがありません。
「使わない週はスキップ」できる柔軟性は、食品ロスを防ぎながら賢く節約したい方にも相性◎。“続けやすさもコスパ”という視点で見ると、毎日の食卓にちゃんと寄り添うのがワタミの宅食ダイレクトの良さです。
メニュー構成・栄養(品数・カロリー・塩分・制限対応 など)
ワタミの宅食ダイレクトは、管理栄養士が献立を設計した冷凍惣菜が特長。主菜と副菜の組み合わせや味付けのバリエーションが考えられており、“ストックから選んでチン”するだけで、平日の夜や忙しい日のあと一品まで手早く整います。
献立は、レンジ加熱後の食感や温度のなじみまで見据えて設計。トレー形状やフィルム構造も扱いやすく、表示どおりのワット数・分数で温めるだけで、手間なく盛り付けまで完了します。
また、冷凍庫の“入りやすさ”も実用面では重要。ワタミの宅食ダイレクトは、宅配便の箱→冷凍庫へダイレクトに収納しやすいサイズ感を意識しており、まとめ買い→計画的に消費というサイクルが作りやすいのも魅力です。
「今日はしっかり主菜を」「軽めに副菜中心で」など、その日の体調や予定に合わせて使い分けられるのが冷凍惣菜の強み。“冷凍庫にある安心感”が、忙しい毎日をそっと後押ししてくれます。
配送・保存条件(配送頻度・冷凍保存期間・調理法 など)
お届けは冷凍の宅配便。全国(一部地域を除く)に対応し、受け取り日時の指定や再配達の調整がしやすいのも宅配便ならではです。留守が多い家庭でも、週末受け取りで1〜2週間分をストックしておく運用が快適。
保存は冷凍庫で。トレーは積み重ねやすく、先入れ先出しで使えばロスを防げます。調理は電子レンジを基本とし、パッケージに記載のワット数と時間に合わせればOK。取り出し時は蒸気やトレーの熱に注意し、やけど対策のため厚手のミトンや布巾を使いましょう。
「次の受け取りまでに食べきれないかも…」というときも、定期のスキップやお休みで柔軟にペースを調整可能。解約手数料がかからないため、生活リズムの変化にもやさしく寄り添います。
“困ったときは冷凍庫。”そんな日常の安心感を、ワタミの宅食ダイレクトが静かに支えてくれるはずです。
2位 nosh(ナッシュ) (ナッシュ株式会社)
価格・送料(1食あたり目安・送料・割引制度 等)
“自分で組む自由度の高さ”を求める人に向くのがnosh。セット価格は構成や数量によって変動し、送料はお住まいの地域や箱数で加算されるスタイルです。まずは生活ペースに合わせて受け取り間隔と箱サイズを決め、「セット価格+送料=1食あたり体感」で把握すると迷いにくくなります。定期で継続するほど割引が進む仕組みがあるため、“まとめ受け取り→冷凍庫で回す”運用がハマるとコストバランスが取りやすいのも魅力。冷凍庫容量や平日/週末の食事リズムに合わせ、少し長いスパンで消費計画を立てるとロスが出にくくなります。
メニュー構成・栄養(品数・カロリー・塩分・制限対応 等)
noshは、メニュー選択の自由度が高く、肉・魚・エスニック・洋食まで幅広いテイストをカバー。好みや気分に合わせて入れ替えや再注文がしやすいので、“飽きにくさ”の面で日常使いに強みがあります。表示情報(カロリーや食塩相当量など)を見比べながら選べるため、平日の夜は軽め、週末は満足感重視などメリハリのある構成が可能。副菜の食感や味のアクセントも意識したメニューが多く、電子レンジでの仕上がりイメージを前提にした設計が習慣化を後押しします。
配送・保存条件(配送頻度・冷凍保存期間・調理法 等)
全国配送の冷凍・宅配便で、受け取りの曜日/時間指定がしやすく、不在がちな人でも回しやすいのが利点。トレーは冷凍庫で積み重ねやすく、“先入れ先出し”を習慣化すればロスなく使い切れます。調理は電子レンジが基本。表示どおりのワット数と時間を守ると仕上がりが安定します。消費ペースが想定より遅れたら、定期のスキップや調整で柔軟にペースダウン。忙しい期間と落ち着く期間の波に合わせて運用できるのが、冷凍宅食の安心感です。
3位 三ツ星ファーム (株式会社イングリウッド)
価格・送料(1食あたり目安・送料・割引制度 等)
三ツ星ファームは、“丁寧な味わいのプレートをストックする”感覚で使える冷凍宅食。セット価格と送料を合算した上で、1食あたりの体感を把握すると計画が立てやすくなります。数量を増やすとトレーの占有スペースが増えるため、冷凍庫の段取りを先に決めておくのがコツ。定期の調整(頻度・数量変更)を活用すれば、「今月は在宅多め→多めに」「来月は外食増→少なめに」といったリズムに合わせてスマートに運用できます。
メニュー構成・栄養(品数・カロリー・塩分・制限対応 等)
主菜の満足感と副菜のバランスに配慮した献立が並び、和洋中の幅広い味わいを日替わりのように楽しめます。表示の栄養情報を参考に、平日用は軽め、週末用はしっかりなど使い分けの設計がしやすいのが利点。“冷凍庫から選んでチン”で完結する手軽さが、忙しい平日夜のハードルを下げてくれます。見た目の彩りや盛りつけのまとまりも皿に移すだけで整うので、在宅ワークの昼食や帰宅後の一皿にちょうど良い印象です。
配送・保存条件(配送頻度・冷凍保存期間・調理法 等)
受け取りは冷凍の宅配便。日時指定や再配達の取り回しがしやすく、まとめて受け取り→計画消費の型を作りやすいのが特徴です。調理は電子レンジで完結。表示のワット数・時間を守り、取り出し時の蒸気・トレーの熱に注意すればOK。トレーは積み重ねやすく、区画ごとに主菜/副菜が分かれているため、食卓に並べても手早く見映えが出せます。消費ペースが合わない時は定期のスキップで無理なく調整しましょう。
4位 DELIPICKS (株式会社DELIPICKS)
価格・送料(1食あたり目安・送料・割引制度 等)
DELIPICKSは、“カジュアルに楽しめる冷凍メニュー”をまとめて届けてもらう感覚で使えるサービス。価格はセットや構成で変動し、送料は地域・箱数等で加算されます。初めは少量×短い間隔で回して消費感覚をつかみ、1食あたりの体感コストを把握したら、生活リズムに合わせて受け取り頻度や数量を最適化。箱のサイズや庫内の空き状況を見ながら“詰め込み過ぎない”運用にすると、日常の負担が減らせます。
メニュー構成・栄養(品数・カロリー・塩分・制限対応 等)
気分で選べる軽快なラインナップが特徴。自分好みのテイストを見つけたら、次回以降はそれを軸に回していくと選ぶ手間が軽減されます。表示の栄養情報を参考にしつつ、“平日は控えめ、週末は満足感重視”のような使い分けも容易。副菜のボリュームや主菜の食べごたえなど、仕上がりのバランスに注目すると、冷凍庫から取り出す優先順位が決めやすく、ローテーションがスムーズになります。
配送・保存条件(配送頻度・冷凍保存期間・調理法 等)
冷凍の宅配便で届き、受け取りは日時指定に対応(詳細は公式を要確認)。トレーは平置き→縦置きなど庫内の空きに合わせて並べ替えると効率的に収まります。調理は電子レンジを基本とし、表示どおりのW数/時間を守るのが美味しさの近道。もし受け取り間隔が合わなければ、スキップや数量変更でペースを微調整しましょう。
5位 食宅便 (日清医療食品株式会社)
価格・送料(1食あたり目安・送料・割引制度 等)
“コースの幅広さ”で選びやすいのが食宅便。セット価格と送料を踏まえ、まずはお試し→継続の判断という段取りが無駄のない始め方です。受け取りを定期化する場合は、箱数と間隔を最適化し、冷凍庫の空きと消費ペースを一致させるのがコツ。食卓の登場頻度が高いほど1食あたりの体感は安定していきます。キャンペーンの有無はタイミングで変わるため、最新の案内を公式で確認してから注文設計を。
メニュー構成・栄養(品数・カロリー・塩分・制限対応 等)
和洋中の定番から季節感のある献立まで幅広く、“平日の定番ローテーション”を作りやすいのが魅力。表示情報(カロリー・食塩相当量など)を目安に、在宅ワークの昼→軽め/夜→しっかりなど使い分けがスムーズです。副菜の食感や風味の変化がつくと満足感が上がるため、主菜の傾向(魚/肉)に合わせたチョイスを意識すると飽きにくくなります。電子レンジ調理が前提のため、仕上がりを想定した盛り付けで食卓の満足度を高められます。
配送・保存条件(配送頻度・冷凍保存期間・調理法 等)
冷凍の宅配便で全国に届きます(詳細条件は公式を確認)。週末にまとめて受け取って冷凍庫に整理しておくと、平日夜の段取りが一気に楽に。加熱はレンジで完結し、表示のW数/分数を守ればOK。トレーのままでも皿に移しても使いやすく、“さっと温めて出せる”安心感が日常の負担を軽くします。消費が追いつかないときは、受け取り間隔を一段伸ばすなど微調整を。
6位 食のそよ風 (株式会社SOYOKAZE)
価格・送料(1食あたり目安・送料・割引制度 等)
食のそよ風は、“日々の食卓にそっと足せる”冷凍宅食。セット価格に加わる送料は地域や箱数で変動するため、受け取りペース×冷凍庫容量を先に決め、そこから数量を逆算すると失敗が少なくなります。まずは少量で感触を確かめ、一週間の消費リズムに合致してきたら箱数を調整。無理なく続けられる回し方を見つけると、1食あたりの体感コストも安定してきます。
メニュー構成・栄養(品数・カロリー・塩分・制限対応 等)
家庭的な味わいの主菜+副菜を中心に、“あと一品を即補充”できる冷凍惣菜の良さが生きるラインナップ。表示情報を見ながら“軽めの日/しっかりの日”を分けると、平日の食卓にリズムが生まれます。冷凍庫から取り出してレンジで温めるだけなので、帰宅が遅い日でも短時間で食卓を整えられるのが魅力。皿に移して温度を落ち着かせるひと手間で、仕上がりの満足度が上がります。
配送・保存条件(配送頻度・冷凍保存期間・調理法 等)
冷凍の宅配便で届き、日時指定に対応(詳細は公式で確認)。受け取り後に外箱をすぐ開封→庫内に平置きして冷凍焼けを防ぎましょう。調理は電子レンジが基本で、表示のW数/時間を守るのがポイント。消費ペースが鈍ったら、受け取り間隔の調整やスキップを上手に使うとロスを抑えられます。冷凍庫の“見える化”(上段=今週分/下段=来週分など)をすると、使い切りやすく運用が楽になります。
7位 ママの休食 (株式会社ママの休食)
価格・送料(1食あたり目安・送料・割引制度 等)
“子育て世代の食卓のあと一品に”を想定したプランが揃うママの休食は、セットごとの価格に地域別送料を加算する方式です。まずは公式ページでプラン一覧と送料テーブルを確認し、「セット価格+送料=1食あたりの目安」を把握しましょう。多めの注文で送料単価が下がるケースもありますが、冷凍庫の空き容量とのバランスが重要。
定期コースを選ぶと毎回自動的に配送されるため、「平日の夜は買い物不要でストックがある安心感」を享受できます。週に1回、2週間に1回など頻度を選べ、必要に応じてスキップや停止も可能。「月2回で庫内管理→余りを防止」といった使い方が、長く続けるコツです。
さらに、初回限定割引や継続割引などおトクなキャンペーンが随時行われているため、最新情報を公式でチェックし、最適プランを選ぶと節約効果が高まります。
メニュー構成・栄養(品数・カロリー・塩分・制限対応 等)
ママの休食は、主菜+副菜の組み合わせで「子どもも大人も食べやすい」味付けが特長です。品目数は多すぎず少なすぎず、一食あたり主菜1品+副菜2品程度で、電子レンジ加熱後の食感を重視したトレー設計です。表示されるカロリー・食塩相当量は、育児中のママ・パパ世帯でも安心して続けられるようにバランスが取られており、「500kcal前後・塩分2.5g未満」を目安に設計されています。
また、アレルギー対応メニューや糖質・塩分控えめメニューなど、制限食オプションも用意されており、家族の健康管理にも活用可能。週ごとにメニューが切り替わる定期便では、“飽きにくいバリエーション”が維持され、冷凍庫から選ぶ楽しさを感じられる工夫が随所にあります。
配送・保存条件(配送頻度・冷凍保存期間・調理法 等)
配送は全国対応の冷凍宅配便を利用。日時指定・時間帯指定が可能で、不在が多い場合も受け取りやすい仕組みです。「平日夜の受け取り→週末にまとめてストック」といった運用が家庭には便利。箱を開封したら、トレーを立てて冷凍庫の奥行きを有効活用し、先入れ先出しを徹底すると品質を保ちやすくなります。
冷凍保存期間は商品ごとに異なりますが、概ね製造日から180日程度。パッケージの賞味期限表示を必ず確認し、早めに消費することが望ましいです。調理は電子レンジで完結し、表示のワット数(500〜600W)・時間(4〜6分)を守ることで、“冷凍惣菜ならではのほぐしやすさ”が発揮されます。取り出し時の蒸気や熱に注意し、ミトンや布巾で安全に取り扱いましょう。
まとめ
本ランキング【2025年版 冷凍宅食比較ランキング7選】では、「冷凍庫にストックしておくだけで、忙しい日も手軽に美味しい一食を用意できる」という共通の利便性を基準に、1位から7位までのサービスを厳選しました。どのサービスも電子レンジで温めるだけというシンプルさを追求しつつ、価格構成や送料体系、メニューのバリエーション、配送の柔軟性などを比較し、日々の食卓がより楽になるプランをピックアップしています。
ランキング上位のワタミの宅食ダイレクトは、管理栄養士が献立を設計し、全国(一部地域除く)へ冷凍惣菜を届ける強みが最大の特徴。続けやすさを重視した休止・変更機能や解約金ゼロの安心感、さらにセット単位でのコストパフォーマンスのバランスも秀逸です。日々の食材調達にかける時間を削減しつつ、栄養バランスも確保できるため、「家族みんなで食卓を囲みたい」「共働きで食事準備が負担」という方々に特におすすめです。
2位のnoshは、メニュー選択の自由度と定期割引によるコストダウンを追求。3位の三ツ星ファームは、味のバリエーションと仕上がりの丁寧さが魅力です。4位DELIPICKSはカジュアルなラインナップで気軽に楽しめ、5位食宅便は豊富なコースと季節感のある献立がローテーションを盛り上げます。6位食のそよ風は家庭的な味わいと手頃感で、「あと一品」をしっかり補充。7位ママの休食は子育て世代のニーズに寄り添ったメニュー設計と柔軟な定期機能が特長です。
冷凍宅食は一度利用システムを理解すれば、“まとめて受け取り→冷凍庫にストック→必要なときにチンするだけ”のルーティンが完成します。初めは送料の確認や冷凍庫レイアウトに少し手間取るかもしれませんが、一度ペースを掴めば急な外出や体調不良時にも安心できるストックが手に入ります。ポイントは、「無理なく続けられる注文頻度」「冷凍庫の収まり」「メニューの好み」の3点を軸に、自分のライフスタイルに合わせた最適化を行うこと。ぜひ本ランキングを参考に、自分や家族にぴったりな冷凍宅食サービスを見つけ、忙しい毎日を美味しくサポートしてください。
冷凍宅食の利便性は、単なる時短だけにとどまりません。新しい旬のメニューに出会えたり、調理のストレスから解放されたり、健康管理のための栄養バランスを意識できたりと、日常を豊かに彩る可能性が広がります。ストックを整えた冷凍庫は、まるで小さなパントリーのように、いざというときの心強い味方。ぜひランキングを眺めながら、“冷凍庫から広がる食の楽しみ”を体験してみてください。