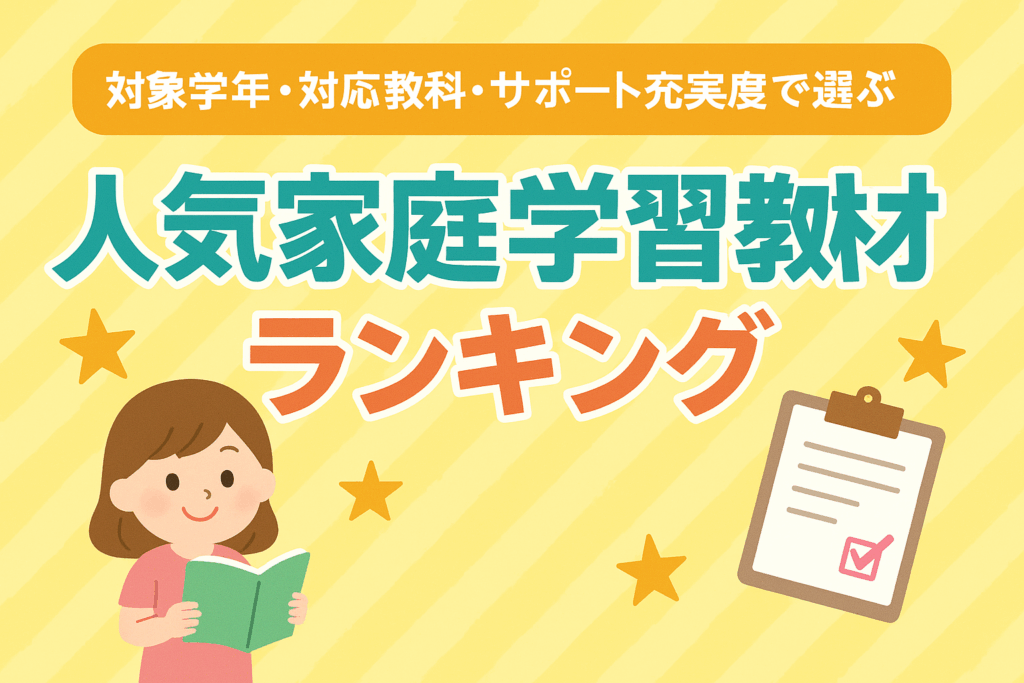
※このページはプロモーションを含みます。
家庭学習教材は、子どもの学力向上や学習習慣づくりに欠かせない存在です。最近では紙教材だけでなく、タブレットやオンライン学習を組み合わせたハイブリッド型も増え、選択肢は多岐にわたります。そこで当サイトでは、対象学年・対応教科・サポート体制といった共通の評価基準をもとに、人気の家庭学習教材をランキング形式でご紹介します。特に1位の教材は、幼児から中学生までを一貫してサポートできる数少ない存在であり、長年の実績と質の高い教材づくりで多くの家庭から支持を集めています。費用面でも続けやすく、親子で一緒に取り組める工夫が満載。忙しい保護者の方でも安心して導入できるのが魅力です。これから教材を選ぶ方はもちろん、すでに利用中の教材を見直したい方にも役立つ情報をお届けします。
ランキングの選定基準
当ランキングでは、家庭学習教材を客観的に比較するため、いくつかの主要な基準を設定しています。まず重要なのは、対象学年の幅です。幼児から中学生までを一貫してサポートできるか、または特定の学年に特化して高い成果を発揮するかを評価します。次に、対応教科の充実度も欠かせません。主要教科だけでなく、副教科や英語などの幅広いカバー力があるかをチェックします。また、学習方式の柔軟性—紙教材、タブレット、オンラインの併用など—は、家庭環境や子どもの学び方に合うかを左右します。さらに、保護者向けのサポート体制(添削、質問対応、進捗管理など)や、コストパフォーマンスも重要視しました。これらを総合的に判断し、ランキングを作成しています。
想定ユーザー・対象学年
今回のランキングは、幼児から中学生までのお子様を持つ保護者を想定しています。学年ごとに求められる教材の役割は異なり、幼児期には学習習慣や好奇心の育成、小学生では基礎学力の定着と学校授業の補完、中学生では定期テストや入試対策が主な目的となります。そのため、幅広い年齢層に対応できる教材はもちろん、特定のステージに特化して高い成果をあげる教材も高く評価しています。特に1位の教材は、幼児・小学生・中学生の各段階で専用カリキュラムを用意しており、家庭学習の成長ストーリーを一貫して描ける点が大きな魅力です。
比較した主な評価軸(学習方式・サポート・費用 など)
評価軸は大きく分けて「学習方式」「保護者サポート」「費用面」の3つです。学習方式では、紙教材の良さを活かしつつデジタルを併用できるか、タブレット完結型か、教材配信や添削の仕組みはどうかを比較しました。保護者サポートでは、添削や質問対応、進捗チェック機能などの有無と質を評価。費用面では、月額料金や追加費用、続けやすさに着目しました。特に1位の教材は、必要な教材のみを厳選し、余計な付録を省くことでコストを抑え、長く続けやすい価格を実現しています。これらの観点から、総合的に優れた教材を上位にランクインさせています。
料金・コース情報の参照方法
各教材の最新の料金やコース内容は、公式サイトで確認することを推奨します。当サイトでは概要をご紹介しますが、教材によっては期間限定のキャンペーンや特典が用意されている場合があります。特に1位の教材は、無料おためし見本の提供を実施しており、実際に教材の質や進め方を体験できます。導入前に試せるこの仕組みは、初めて家庭学習教材を利用するご家庭にも安心感を与えます。
体験申込・資料請求リンクの扱い
体験や資料請求は、教材選びの判断材料として非常に有効です。当サイトで紹介する全ての教材は、公式サイトへのリンクを掲載しており、そこから直接申込ページにアクセスできます。特に1位の教材は、各学年専用の資料やおためし教材の提供が充実しており、教材の雰囲気をしっかり確認してから導入できます。
注意事項(価格や仕様の変更可能性 など)
教材の価格や仕様は、改訂やキャンペーンなどにより変更される可能性があります。必ず最新情報は公式サイトで確認してください。また、学習効果や適性はお子様によって異なるため、教材選びは体験版や見本を活用しながら慎重に行うことをおすすめします。当ランキングはあくまで比較の参考としてご活用ください。
| 順位 | ショップ名/サービス名 | 対象学年 | 学習方式 | 保護者サポート | 教科対応 | 価格帯の傾向(目安) | 特徴ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ポピー | 幼児〜中学 | 紙中心+補助デジタル | 丸付けガイド等・学習見守り | 基礎〜定期テスト | 続けやすい価格感 | 余計な付録を省き必要十分を厳選でコスパ良好 |
| 2位 | 進研ゼミ | 幼児〜高校 | 紙+タブレット | 添削・質問・学習アプリ | 主要教科+英語等 | 中〜 | 教材・アプリが充実 |
| 3位 | Z会の通信教育 | 幼児〜大学受験 | 紙/タブレット選択 | 添削・質問 | 発展〜受験 | 中〜高 | 思考力重視の良問 |
| 4位 | スマイルゼミ | 幼児〜中学 | タブレット完結 | 自動採点・みまもり | 主要教科+英語等 | 中〜 | 端末一台で完結 |
| 5位 | スタディサプリ | 小〜高 | 動画学習(オンライン) | 学習管理 | 主要教科 | 低〜中 | 一流講師の講義動画 |
| 6位 | デキタス | 小・中 | オンライン演習 | 見守り・質問フォーム | 主要教科 | 中 | 学校の授業準拠 |
| 7位 | RISU算数 | 年長〜小 | タブレット(算数特化) | 学習データで個別最適 | 算数 | 中〜高 | 先取り・つまずき解析 |
| 8位 | WonderBox(ワンダーボックス) | 年中〜小 | アプリ+キット | 保護者向け案内 | STEAM/思考系 | 中 | 探究心を育む設計 |
| 9位 | 天神 | 幼児〜中学 | PC/タブレット | 学習相談 | 主要教科等 | 高 | カリキュラムが豊富 |
| 10位 | こどもちゃれんじ | 0歳〜年長 | 紙+知育玩具+アプリ | 保護者向け情報 | 生活・知育・ことば等 | 中 | 年齢別で楽しみやすい |
1位 ポピー(株式会社新学社)

出典:株式会社新学社
対象学年・対応教科
ポピーは「幼児・小学・中学」を一貫サポートする点が大きな魅力です。幼児期は、文字・数・言葉に触れながら、読み聞かせや運動遊び、しつけを含むバランスの良い土台づくり。小学生では使用教科書に合わせた内容で授業とシームレスに連動し、短時間でも効率よく基礎〜標準を定着。中学生は定期テストや内申を意識した内容で、実技教科まで見据えた学習が可能です。英語は「ポピー Kids English」で年齢に応じた3レベルを用意し、音声ペンや物語教材で自然な音への慣れを促します。学年が上がっても継続しやすい編成で、家庭学習のステップアップが描きやすい点が支持されています。
学習方式(紙/タブレット/併用)
ポピーのコアは「書いて身につく」紙教材。視覚・運筆・音読といった基本動作を取り入れ、落ち着いて学べることが特長です。必要十分に厳選された問題量で学習負担が過度になりにくいため、毎日の学習習慣づくりにも向きます。デジタルは補助的に活用するスタンスで、紙での定着を中心に据える構成が、低学年でも取り組みやすいという声につながっています。紙中心×デジタル補助のバランスは、端末依存を避けたいご家庭や、親子で答案・解説を見ながらコミュニケーションを取りたい家庭にもマッチします。
保護者向けサポート(添削・質問対応・見守り機能)
家庭学習が続くかどうかは、保護者の負担感にも左右されます。ポピーは、丸付けや声かけのコツなど、家庭で実践しやすいサポート情報を提供し、親子のやり取りをスムーズに。学年ごとの「取り組み方ガイド」など、伴走しやすい設計が好評です。余計な付録や操作を増やさないため、準備・片付けがシンプルで、学習リズムが崩れにくいのもポイント。結果として、毎日コツコツ進める仕組みが根づきやすく、テスト前の総復習にも移行しやすい導線が描けます。初めてのご家庭でも取り組みやすいよう、おためし見本で体感できる導入ステップが用意されているのも安心材料です。
2位 進研ゼミ(株式会社ベネッセコーポレーション)
対象学年・対応教科
進研ゼミは幼児から高校まで幅広くラインアップされ、学年別に必要な力を段階的に伸ばせる編成が魅力です。小学生は国算理社と英語、さらにプログラミングなど周辺領域まで視野を広げ、学年に即した到達目標を積み上げていけます。中学生では定期テスト・入試を見据えた学習計画が組みやすく、教科横断で理解を深める設計。幼児は遊びと学びの融合で、文字・数・思考の基礎を楽しく育てられるのが特長です。学習進度や興味に応じて教材量や取り組み方を調整しやすく、兄弟姉妹での併用にも向いています。
学習方式(紙/タブレット/併用)
紙教材とタブレット活用のハイブリッドにより、書いて定着×デジタルで演習量の両立を図れるのが強み。自動採点や映像解説で理解の抜けを素早く補い、紙では記述力・説明力を鍛える、といった役割分担が明確です。家庭の端末環境や方針に合わせてスタイルを選びやすく、学習の導線がシンプル。付録やアプリのモチベーション設計も充実しており、毎日の「続ける仕組み」が作りやすいのもポイントです。
保護者向けサポート(添削・質問対応・見守り機能)
添削・質問サポート、学習到達度の可視化、進路・子育て相談など、家庭の伴走を前提とした支援が豊富です。取り組み状況が見えることで声かけのきっかけが増え、テスト前の計画や弱点補強にもつなげやすい構成。紙とデジタル両面のガイダンスが整っており、初めてでも運用の負担が増えにくい点が評価されています。
3位 Z会の通信教育(株式会社Z会)
対象学年・対応教科
幼児〜大学受験までを網羅し、思考力・記述力を段階的に鍛える系統設計が持ち味。小学生は基礎から発展へステップアップ、中学生は入試を見すえた応用力の土台づくり、高校生は受験戦略に直結する科目別強化が行いやすい構成です。英語・数学などの主要教科は深い理解を促す問題で、知識の定着と活用の両輪を意識。教科横断での読解や記述にも自然に触れられるため、学びの質を上げたい層に適します。
学習方式(紙/タブレット/併用)
紙中心/タブレット中心を学年や目的に応じて選べるのが特徴。紙では精選された良問にじっくり取り組み、解法過程を書ききる体験を重視。タブレットでは採点・復習の回転を上げ、弱点範囲を素早く補強できます。いずれも「自分で考え抜く時間」を設計に組み込んでおり、粘り強い学習姿勢の育成に寄与します。
保護者向けサポート(添削・質問対応・見守り機能)
添削の質とフィードバックの丁寧さに定評があり、答案の良し悪しが言語化されたコメントで返ってくる点が魅力。質問対応や活用ガイドも整備され、保護者は「学習の深度」を見守りやすい環境です。量より質を重視するため、限られた時間で学習効果を最大化したい家庭に向きます。
4位 スマイルゼミ(株式会社ジャストシステム)
対象学年・対応教科
幼児〜高校までラインアップされ、主要教科を中心に学校学習の定着を図りやすい構成。学年ごとの到達目標が画面で見えるため、ゴールから逆算した取り組みがしやすいのが特長です。英語やプログラミング等の周辺領域も扱い、広く・薄くではなく着実に積み上げたい層にフィットします。
学習方式(紙/タブレット/併用)
専用タブレット完結型で、書き味と自動採点を活かしながら演習の回転を高められます。アニメーション解説やつまずき検知で理解の抜けを素早く補い、宿題・予習復習のペースメイクが容易。端末一台で管理できるため、教材の散逸が起こりにくく、片付け・準備の手間も少ないのが利点です。
保護者向けサポート(添削・質問対応・見守り機能)
「みまもる」系の機能により学習時間・到達状況を可視化。保護者はアプリで進捗を確認し、声かけのタイミングを逃しにくくなります。紙を使わない分、ノート運用や記述面のフォローを家庭で補うとバランスが取りやすく、デジタルで主体的に学ぶ習慣づくりに向きます。
5位 スタディサプリ(株式会社リクルート)
対象学年・対応教科
小〜高まで対応の動画学習サービス。プロ講師のわかりやすい授業を短時間で視聴でき、部活や習い事と両立しやすいのが強みです。主要教科中心に単元が細かく刻まれており、苦手範囲だけをピンポイントで補強したい場面でも活用しやすい設計。復習から先取りまで幅広く使えます。
学習方式(紙/タブレット/併用)
オンライン動画+演習のスタイルで、いつでも・どこでも・何度でも学べるのが魅力。視聴速度の調整や章末確認で理解度をセルフチェックし、必要に応じて紙ノートと併用すると定着が高まります。自学自習の基礎体力を身につけたい層におすすめです。
保護者向けサポート(添削・質問対応・見守り機能)
学習履歴の可視化やリマインド機能により、家庭での声かけをしやすくします。紙の添削は前提にしないため、自走の仕組み作りが鍵。視聴と演習のリズムを家庭で設け、短時間×高頻度で回すことで成果につながりやすくなります。
6位 デキタス(株式会社城南進学研究社)
対象学年・対応教科
小・中学生向けに、学校の授業内容の理解・定着に焦点を当てた構成。主要教科の単元が学校進度に沿って整理されており、授業での「わからない」を家庭で素早く補えるのが強みです。さかのぼり学習で前学年に戻りやすく、テスト前の総点検にも使いやすい作りになっています。
学習方式(紙/タブレット/併用)
ブラウザベースのオンライン学習で、PC/タブレットがあれば機器追加なしで始めやすいのが魅力。映像授業→演習→復習のサイクルが短く、理解と問題演習の往復でスモールステップの達成感を積み重ねられます。日々の宿題・小テスト対策にも適しています。
保護者向けサポート(添削・質問対応・見守り機能)
進捗の可視化や質問フォームの整備など、家庭で見守りやすい導線が特徴。負担を増やさずに学習状況を把握でき、必要なときにポイントを絞って声かけができます。続けやすい運用を意識した設計で、学習習慣を安定させたいご家庭に向きます。
7位 RISU算数(RISU Japan株式会社)
対象学年・対応教科
RISU算数は年長〜小学生を中心に、算数に特化した学習体験を提供します。学年という区切りに縛られず、到達度に応じて前後の単元へ柔軟に移動できるスモールステップ設計が秀逸で、得意単元はどんどん先へ、苦手単元は基礎に戻ってじっくり取り組めます。図形・文章題・思考力問題など、各領域をバランス良く配置し、低学年でつまずきやすい「繰り上がり・繰り下がり」や「わり算の意味」などを視覚的・体験的に納得させる工夫が見られます。算数一本に集中するため、他教科との広がりは別サービスで補う設計になりますが、算数の土台をがっちり固めたい家庭には特にマッチします。
学習方式(紙/タブレット/併用)
タブレット中心の学習で、回答履歴から弱点を解析して出題を最適化。紙のノートと併用すると、途中式や図の書き起こしを伴う深い理解につながります。画面上の誘導に頼りすぎない問題構成で、自分の頭で考え抜く時間を確保。正解・不正解の反応が速く、テンポよく回せるため、毎日の短時間学習に組み込みやすいのも利点です。長期休みの先取り・総復習にも活用しやすく、学習の「止まり」を作らない運用が可能です。
保護者向けサポート(添削・質問対応・見守り機能)
学習データに基づくレポートで到達度が確認でき、声かけのタイミングを掴みやすいのが特徴。つまずきが見えたら、単元をさかのぼる提案でリカバリーの道筋が明確になります。添削ベースではなく自動フィードバック中心のため、家庭ではノート運用や説明させる時間を意識的に作ると、記述力・表現力の補完が進みます。先取りしすぎによる理解の浅さを防ぐため、定着チェックの小テストを習慣化すると運用が安定します。
8位 WonderBox(ワンダーボックス)(ワンダーラボ株式会社)
対象学年・対応教科
ワンダーボックスは年中〜小学生を主対象に、STEAM領域や思考力・創造性に重心を置いた教材です。いわゆる教科書準拠の「学力」を直接伸ばすというより、探究心・問題発見力・試行錯誤といった非認知的な力の土台を育てます。パズル、プログラミング的思考、アート的活動など、多角的なアプローチで「考えることが楽しい」状態を引き出し、結果的に算数・理科などの理解に波及効果をもたらす設計。主要教科の演習は別教材で補いながら、学びの好奇心を育てたい家庭に合います。
学習方式(紙/タブレット/併用)
アプリ課題と実物キットのハイブリッドが特徴で、手を動かしながら発想を形にしていくプロセスが中心。タブレット上の課題は直感的な操作で取り組め、キットでは素材の触感や立体感を伴う体験を通じて、空間認識・組み立て力などを伸ばします。紙ワークのような「書く訓練」は少なめなので、家庭で読み書きの基礎練習を補うとバランスが取れます。週数回・短時間でも効果を感じやすく、息抜きのように楽しめるのも強みです。
保護者向けサポート(添削・質問対応・見守り機能)
保護者向けの取り組みガイドや作品の共有・振り返りの導線が用意され、子どもの発想を引き出す声かけ例も参考になります。添削型ではありませんが、成果物にコメントを返したり、家族で展示会のように見せ合う時間を作ると、自己表現のモチベーションが高まります。評価を点数で示さない分、プロセスを楽しむ姿勢を家庭で醸成できるかが鍵。教科の定着と並走する「第二の学び軸」として機能します。
9位 天神(株式会社タオ)
対象学年・対応教科
天神は幼児〜中学生まで幅広く、基礎から応用まで系統立てて学べるコンテンツが豊富です。主要教科に加え、学年や目的に応じた細かな教材が揃うため、家庭の方針に合わせたカスタマイズが行いやすいのが特長。定期テスト対策や先取り・さかのぼりに柔軟に対応でき、単元の網羅性を重視するご家庭に向きます。ボリュームが多い分、最初にゴール設定と時間配分を決めると運用がスムーズです。
学習方式(紙/タブレット/併用)
PC/タブレット中心のデジタル学習で、解説→演習→確認のサイクルをテンポよく回せます。紙のノートと併用して要点を書き出す習慣をつけると、定着度が一段上がる印象。教材量が豊富なため、今日やる範囲を先に決める運用がコツで、迷わず着手→完了までの導線を短く保てます。映像・スライド・問題の組み合わせで視覚的に理解しやすいのも利点です。
保護者向けサポート(添削・質問対応・見守り機能)
学習履歴の確認や、進め方に関するガイドが用意され、自主学習の設計を家庭でサポートしやすい構成です。添削ベースではないため、理解の甘い単元は家庭で口頭テストを挟む、チェックリストを作るなど、見守りの工夫が効果的。教材の選択肢が多い分、定期テストや模試の日程から逆算し、「いつ・どこまで」を可視化すると、学習が走りやすくなります。
10位 こどもちゃれんじ(株式会社ベネッセコーポレーション)
対象学年・対応教科
こどもちゃれんじは0歳〜年長を対象に、生活習慣・言葉・数・思考・社会性を遊びの中で育む構成が魅力です。年齢に応じたテーマとストーリーで、「できた!」を積み重ねる設計が秀逸。小学校入学までに身につけたい基礎的な生活スキルと学びの土台を、自然な流れで習慣化できます。教科学習そのものというより、入学準備の総合力を育成する位置づけで、学ぶことへの前向きさを醸成します。
学習方式(紙/タブレット/併用)
紙のワークや知育玩具、映像コンテンツ、アプリを組み合わせ、五感を使った体験で理解を促します。手先を使う作業やごっこ遊びを通じて、言葉のやり取り・ルール理解など非認知面にも働きかけます。家庭ではワークの提出物や遊びの成果を写真に残すなど、成長の見える化をすると励みになります。低年齢から取り組みやすく、毎月の到着が学習の合図になるのも継続のコツです。
保護者向けサポート(添削・質問対応・見守り機能)
月ごとの取り組みガイドや声かけ例、入学準備に関する情報など、育児と学びの橋渡しとなるサポートが充実。添削型ではありませんが、親子で一緒に取り組むことを前提に設計され、成功体験を家庭内で称賛する文化を作りやすいのが強みです。教材が増えて散らばりがちな点は、収納ボックスや曜日ルールで運用を整えると、無理なく継続できます。
まとめ
本ランキングでは、対象学年・対応教科・学習方式・保護者サポートという共通の評価軸を据え、家庭の実情に合わせて選びやすいよう情報を整理しました。
一方で、学習の成果は教材だけで決まるものではありません。家庭の学習リズムの設計が肝心で、1日の中の「いつ・どこで・どの順で」取り組むかを最初に決めると、迷いが減り継続率が上がります。特にデジタル教材は、ログインから学習開始までの導線を短く保ち、終わったら“できたことメモ”を親子で共有するだけでも、定着度とモチベーションが変わります。紙中心の教材の場合は、丸付けの時間をあらかじめブロックし、ほめるポイントを1つで良いので毎回見つけると、次の着席が早くなる傾向があります。
価格面は、継続可能性を左右する重要な要素です。「費用は固定費」という認識で家計に組み込むと、解約・再契約のコストや学習リズムの乱れを防げます。ボリュームが多い教材は「全部やる」ではなく、優先単元を決めて“完了を積み上げる”運用へ。逆にボリュームが絞られた教材では、ノート追記や口頭説明を足して、アウトプット密度を高めると効果が伸びます。デジタルは復習回転、紙は記述の深さ——それぞれの特性を併用して、理解×定着の両輪を回すイメージが理想です。
なお、本ランキングの第1位である「幼児・小学・中学ポピー」は、必要十分に厳選された紙教材×補助デジタルの組み合わせにより、学習負担を過度に増やさず続けやすい構成が高く評価されました。幼児から中学までの一貫性、教科書に沿った設計、保護者が伴走しやすい運用ガイドなど、“家庭で回る”仕組みが細部まで行き届いています。余計な付録を抑えたコスト設計も、継続のハードルを下げる重要なポイント。「まずは習慣」を最優先にしたいご家庭にとって、スタートのしやすさと安定感が際立つ選択肢と言えるでしょう。
最終的には、お子さまの性格・現在地・家庭の方針との相性が何より大切です。迷ったら、体験・見本・無料おためしで実際の使用感を確かめ、1〜2週間の“お試しスケジュール”を組んでみてください。カレンダーに学習枠をブロックし、終わりに親子で「今日の1行ふり返り」を書けば、教材の違いがクリアに見えてきます。あなたのご家庭にぴったりの一冊(一本)が見つかりますように。